福岡県久留米市安武町にある「まつもと整形外科」
こんにちは![]() まつもと整形外科の骨粗鬆症マネージャーです
まつもと整形外科の骨粗鬆症マネージャーです![]()
今回は『運動&食事で強い骨を手に入れる!』をテーマにお話させていただきます!
目次
骨粗しょう症予防の基本:運動と食事
骨粗しょう症予防の基本は運動と食事です。運動は主に骨密度を向上させ、骨折リスクを低減する効果があります。具体的な運動としては、ウォーキングや筋力トレーニングが挙げられます。一方、食事は骨の健康を維持する上で重要な役割を果たし、カルシウムやビタミンDなどの栄養素の摂取が大切です。
まず運動においては、筋力とバランスを鍛えることが骨折予防に役立ちます。特に高齢者や女性において、転倒による骨折が増加する傾向があります。適度な運動を継続することで、筋力の低下やバランスの悪化を防ぐことができます。
また、運動は骨密度の維持にも効果があります。骨密度は年齢とともに減少していくため、適度な運動や負荷をかけることで骨に刺激を与えて、骨組織の生成を促進し、骨密度の低下を抑えることができます。
食事については、カルシウムやビタミンDなど骨に良い栄養素をバランスよく摂取することが大切です。特にカルシウムは骨の主成分であり、ビタミンDはカルシウムの吸収を助ける働きを持っています。これらの栄養素が不足すると、骨の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
最後に、生活習慣の改善も骨粗しょう症予防に役立ちます。禁煙・適度な飲酒・ストレスの軽減など、全体的な健康状態を整えることで、骨の健康も向上します。
骨粗しょう症予防に効果的な運動法
骨粗しょう症予防に効果的な運動法には、ウォーキングや筋力トレーニングがあります。これらの運動は骨密度を向上させ、骨折リスクを低減する効果が期待できます。
ウォーキングは、筋力・バランス・骨密度の向上に役立ちます。特に高齢者や女性では、転倒や骨折のリスクが高まるため、定期的なウォーキングを習慣化することが重要です。また、ウォーキングは気軽に取り組める運動であり、特別な道具も必要ありません。
筋力トレーニングでは、大腿四頭筋や腰周りの筋肉を強化することが骨粗しょう症予防に役立ちます。スクワットや膝立て運動などのシンプルなエクササイズを行うことで、筋力を向上させることができます。ただし、過度の負荷は膝関節や股関節痛の原因となったり、逆に骨折リスクを高める可能性があるため、無理をせず適度な強度で継続的に行うことが大切です
また、体操やヨガ、ピラティスなどの柔軟性やバランスを鍛える運動も、骨粗しょう症予防に効果的です。これらの運動を取り入れることで、筋肉の柔軟性を高め、転倒や骨折のリスクを低減することが期待できます。
運動や食事・生活習慣改善によって、骨粗しょう症の予防が可能です。是非、日々の生活の中で意識的に取り入れていきましょう。

ウォーキング:適度な負荷をかける方法
ウォーキングは、適度な負荷をかけることで、骨折予防や骨粗しょう症対策に効果的な運動となります。歩行によって足や膝、腰などの関節や骨に適切な刺激が与えられ、骨密度が向上しやすくなるからです。
◯ウォーキング中には、姿勢を良くし、バランス感覚を養うことが重要です。
◯時間は、月に1~2回程度のウォーキングよりも、毎日20~30分の短時間で継続する方が効果が得られやすくなります。
◯必要に応じて、専門家に相談し、適切なウォーキング方法を学ぶことがおすすめです。
適度な負荷を与えながら長期的に続けることで、健康的な生活を送ることが可能です。

ジョギング:筋力強化と骨密度アップ
ジョギングは筋力強化と骨密度アップに効果的な運動方法です。適切な負荷をかけることで、骨密度が向上し、骨折リスクが低減します。
◯ジョギングは、週に2~3回、20~30分程度の運動を継続することが望ましいです。
◯病院やスポーツクラブで指導を受け、正しいフォームやトレーニング方法を学ぶことが重要です。
◯積極的に身体を動かすことで、筋肉のバランスが整い、転倒リスクが減少します。
ジョギングを続けることで、健康的な骨づくりができるでしょう。
家庭でできる運動:開眼片脚立ちやストレッチ
家庭でできる運動として、開眼片脚立ちやストレッチがあります。これらの運動は、簡単に実践でき、骨密度アップや筋力強化に役立ちます。具体的には次のような方法があります。
◯開眼片脚立ちは、足首周りの筋力を鍛え、転倒予防につながります。立った状態で片足を持ち上げ、15~30秒程度バランスを保つことを繰り返します。
◯ストレッチは、筋肉の柔軟性を高め、関節の動きをスムーズにします。例えば、大腿四頭筋やハムストリングスのストレッチが効果的です。
家庭で行う運動も、継続することが大切です。
高齢者の運動方法:無理なく続けられる工夫
高齢者におすすめの運動方法として、無理なく続けられる工夫が大切です。具体的には以下のようなポイントが挙げられます。
◯やりすぎない:適切な負荷をかけることで効果が得られるため、無理なく続けられる運動を選択することが重要です。
◯身近な活動を取り入れる:例えば、階段を使った運動や家事を通じて、筋力を維持・向上させることができます。
◯安全性を確保する:運動中に転倒しないよう、安全性を考慮した運動を行うことが望ましいです。
無理なく続けられる運動を実践することが、高齢者にとって最も効果的な骨密度アップ法となります。
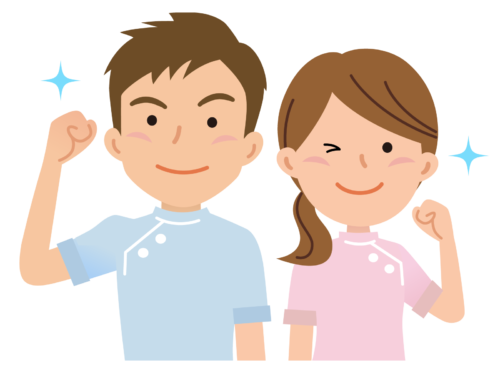
転倒予防とバランス感覚の向上
転倒予防やバランス感覚の向上は、骨折のリスクを減らす重要なポイントです。運動は骨密度を維持し、筋力を強化する効果も期待できます。特に、ウォーキングやジョギングは筋力とバランス感覚の向上に役立ちます。加えて、足と腰の筋肉を鍛えるトレーニングも効果的です。
栄養面でも改善が必要で、カルシウムやビタミンDの摂取が大切です。これらの成分が不足すると骨密度の低下や骨粗しょう症が進行しやすくなります。健康的な食事習慣も骨密度維持には欠かせません。
また、病院での定期的な骨密度検査が推奨されます。骨密度の低下に早く気づくことができれば、適切な治療や生活の改善に取り組むことができます。
骨密度検査の重要性:定期的なチェックが大切
骨密度検査は、骨粗しょう症の診断や治療の進行をチェックするために必要不可欠です。骨密度が低下すると、骨折リスクが高まります。そのため、年齢や状態に応じた適切なタイミングでの検査が大切です。
検査方法にはいくつかの種類がありますが、最も推奨されている検査はDEXA(デュアルエネルギーX線吸収測定法)と呼ばれるものです。
骨密度検査の結果は、YAM値で評価し、YAM値が低い場合は骨折の危険が高く、適切な治療や予防策を提案します。骨密度検査は簡単で無痛であり、定期的に受けることで骨の健康状態を把握できます。検査のタイミングや頻度は、一人ひとりの状況により異なるため、医師と相談して決めましょう。

閉経後の女性の検査タイミング
閉経後の女性は、骨密度が低下しやすいため、骨密度検査のタイミングが特に大切です。閉経直後は、骨密度が急激に減少するリスクがあるため、少なくともこの時期には検査を受けることが推奨されます。以降は、医師の指示に従って定期的に検査を受けましょう。
また、閉経後に骨折を経験した場合や、体重の減少、姿勢の変化など、骨密度の低下を示唆する症状がある場合は、速やかに検査を受けることが重要です。これによって、骨密度の低下が判明すれば適切な対策を講じることができます。
骨密度が低下した場合の対処法
骨密度が低下した場合、医師と相談しながら適切な対策を講じましょう。薬物療法やサプリメントの摂取のほか、適度な運動や食生活の改善が必要です。
骨密度の低下は、継続的な対策が効果を発揮するため、日々の生活習慣の見直しを怠らないようにしましょう。健康的な骨を維持するために、一緒にがんばりましょう!
骨粗しょう症の8割近くを女性が占めており、女性ホルモンの低下する更年期以降に多くみられます。閉経を迎える50歳前後から骨量は急激に減少し、60歳代では2人に1人、70歳以上になると10人に7人が骨粗しょう症と言われています。40歳を過ぎたら、年1回は検査をすることが望ましいとされています!
当院で行っている骨粗しょう症検査・治療については以下のページで詳しくご紹介しています!ぜひご覧ください☆
↓↓↓
TELでのお問い合わせもお待ちしております!
📞0942-27-0755【参考文献】
・骨粗鬆症財団,どんな運動が必要? https://www.jpof.or.jp/osteoporosis/motion/training.html
・骨粗鬆症財団,骨粗鬆症予防・改善体操 https://www.jpof.or.jp/Portals/0/images/publication/leaf_03_181003.pdf























