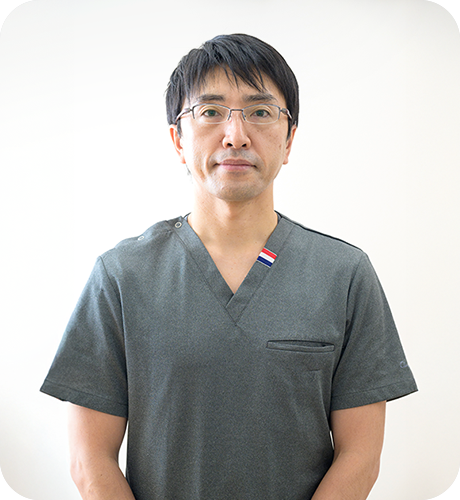ロコモティブシンドロームってご存知ですか!?
まつもと整形外科は福岡県久留米市安武町にある、整形外科・リハビリテーション科・スポーツ整形外科のクリニックです!!
こんにちは!
久留米市安武町にある整形外科クリニック まつもと整形外科 院長 松本淳志です
目次
ロコモティブシンドロームとは?セルフチェックと予防のための運動法
近年、「ロコモティブシンドローム」という言葉を耳にする機会が増えました。超高齢社会を迎えた日本では、ロコモティブシンドロームは誰にでも起こりうる重要な健康課題の一つです。
今回は、ロコモティブシンドロームとは何か、どのように予防・対策をすれば良いのかについて詳しく解説し、簡単にできるセルフチェックや運動方法もご紹介します。
ロコモティブシンドロームとは?
ロコモティブシンドロームとは、運動器(筋肉・骨・関節など)に障害が起こり、運動器の衰えによって、立つ・歩くといった移動機能が低下し、歩行や日常生活に支障をきたす状態のことを指します。日本整形外科学会が提唱した概念で、略して「ロコモ」とも呼ばれます。
ロコモが進行するとどうなる?
ロコモが進行すると、次のようなリスクが高まります。
-
-
転倒・骨折のリスク増加
-
-
-
要介護状態への移行
-
-
-
外出機会の減少による社会的孤立
-
-
-
心身機能の低下(フレイルや認知症との関連)
-
つまり、健康寿命(元気で自立した生活を送れる期間)を短くする要因となるのです。
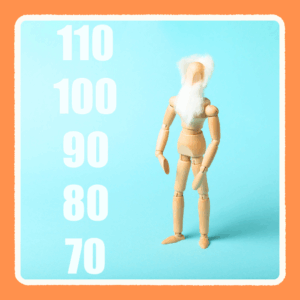
健康寿命(元気で自立した生活を送れる期間)を短くする要因
ロコモの主な原因
ロコモの背景には、以下のような原因が挙げられます。
-
-
加齢による筋力低下(サルコペニア)
-
-
-
骨粗しょう症による骨の脆弱化
-
-
-
変形性膝関節症や脊柱管狭窄症などの関節・脊椎疾患
-
-
-
運動不足・活動量の低下
-
-
-
肥満や生活習慣病(糖尿病・高血圧)との関連
-
つまり、「運動器の老化」と「生活習慣」が深く関係しているのです。
ロコモ度をチェック!セルフチェックで今の状態を把握しよう
まずは、自分がロコモかどうか、簡単にセルフチェックしてみましょう。以下の7項目のうち、1つでも当てはまるとロコモの可能性ありとされています。
ロコモ25から抜粋したセルフチェック項目
- 片脚立ちで靴下が履けない
- 家の中でつまずいたり、滑ったりする
- 階段を上るのに手すりが必要である
- 横断歩道を青信号のうちに渡りきれない
- 15分以上歩き続けることができない
- 2kg程度の買い物袋を持ち帰るのが困難
- 掃除機がけや布団の上げ下ろしがつらい
1つでも該当すれば、要注意です!

チェックをしてみましょう
ロコモ予防の鍵は「運動」!なぜ運動が必要なのか?
ロコモを防ぐためには、運動習慣の維持と筋力の向上が何より重要です。運動によって得られる効果は以下のとおりです。
運動の主な効果
-
-
筋力とバランス力の維持・向上
-
-
-
骨密度の維持(骨粗しょう症予防)
-
-
-
血流改善による関節痛の軽減
-
-
-
転倒・骨折のリスク低下
-
-
-
自律神経や認知機能の活性化
-
とくに下肢筋力の低下がロコモに直結するため、脚の筋肉を鍛える運動が推奨されています。
おすすめのロコモ予防運動【自宅で簡単!】
1. 片脚立ち(バランス能力の維持)
-
-
方法:壁に手を添え、片脚で立ちます。左右1分ずつが目安。
-
-
-
ポイント:慣れてきたら、手を使わず行ってみましょう。
-
2. スクワット(下肢筋力の強化)
-
-
方法:肩幅に足を開き、ゆっくり腰を下ろして戻します。10回×2セット。
-
-
-
ポイント:膝がつま先より前に出ないよう注意しましょう。
-
3. もも上げ(体幹と股関節のトレーニング)
-
-
方法:椅子に座った状態で片脚を膝から上に引き上げます。左右10回ずつ。
-
-
-
ポイント:腹筋を意識して行うと効果的です。
-
4. つま先立ち(ふくらはぎの筋力強化)
-
-
方法:椅子の背に手を添えて、かかとを上げてつま先立ちになります。10回×2セット。
-
-
-
ポイント:姿勢をまっすぐ保ちましょう。
-

適切な運動をしましょう
ロコモは早期発見・早期予防がカギ!
ロコモは自覚症状が出にくいため、気づかないうちに進行してしまうことがあります。
しかし、早い段階から対策すれば、進行を防ぎ、健康寿命を延ばすことが可能です。
以下のような方は、早めの対策をおすすめします。
-
-
60歳以上で運動習慣が少ない
-
-
-
骨粗しょう症と診断されたことがある
-
-
-
膝や腰の痛みで歩くのがつらい
-
-
-
家の中でも転びそうになることが増えた
-
当院では、理学療法士によるロコモ予防のリハビリ指導や筋力評価、姿勢分析なども行っております。
少しでも不安がある方は、お気軽にご相談ください。
まとめ
ロコモティブシンドロームは、誰もがなり得る「将来の介護リスク」を高める状態です。
しかし、適切な運動習慣と生活の見直しで予防・改善が可能です。
まずはセルフチェックで現状を把握し、自宅でできる運動からはじめてみましょう。
そして、不安があれば早めの受診や専門的なサポートを受けることが大切です。
\ 健康寿命をのばす第一歩、今日から始めましょう!/
まつもと整形外科には国家資格を持つ理学療法士・作業療法士が計26名在籍しています。患者さま一人ひとりに合った専門性の高いリハビリメニューを提供させていただきます。
・日本整形外科学会、ロコモティブシンドローム(ロコモ)とはhttps://www.joa.or.jp/public/locomo/index.html
・長寿科学振興財団、ロコモティブシンドロームとはhttps://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/locomotive-syndrome/about.html
・日本生活習慣病予防協会、ロコモティブシンドローム/サルコペニア/フレイルhttps://seikatsusyukanbyo.com/guide/locomotive.php